052-870-9725

1. 基本理念
利用者の心身の自由は基本的人権の一部であり、これを制限する身体拘束は、利用者の尊厳を著しく損ない、心身に悪影響を与える行為である。
当事業所は、利用者の尊厳と権利を最優先に、身体拘束等の廃止と適正化を推進する。
2. 身体拘束等の禁止原則
- 身体拘束、行動制限、その他利用者の身体の自由を不当に制限する行為は、原則として行わない。
- 「身体拘束等」とは、利用者の行動を物理的または薬物的に制限し、その自由を奪う行為を指す。例:
- ベルトやひも等による体幹・四肢の固定
- ベッドからの離床を防ぐための柵や機器の設置
- 移動・発声を制限する行為
3. やむを得ず身体拘束等を行う場合の3要件
以下のすべてを満たす場合に限り、最小限の範囲・時間で実施する。
- 切迫性:本人または他者の生命・身体に重大な危険が差し迫っている場合
- 非代替性:他に代替する介護方法がない場合
- 一時性:一時的な対応であり、速やかに解除が可能である場合
4. 実施手続き
やむを得ず身体拘束等を行う場合は、次の手順に従う。
- 管理者・虐待防止責任者へ報告し、承認を得る(緊急時を除く)
- 実施理由、方法、開始・終了時間、実施者名を記録する
- 利用者および家族に事前に説明し同意を得る(緊急時は事後説明)
- 必要最小限の時間で行い、終了後は速やかに解除する
- 実施後は利用者の心身の変化を観察し記録する
5. 記録・保存
- 実施した場合は「身体拘束等実施記録」に詳細を記入し、5年間保存する。
- 虐待防止委員会または身体拘束適正化委員会にて事例を検証し、代替手段や再発防止策を検討する。
6. 検証体制
- 委員会は年2回以上開催し、身体拘束等の実施状況や改善策を協議する。
- 委員会結果は全職員に周知し、ケアの改善に活かす。
7. 日常的な拘束回避の取組
- 利用者の主体性を尊重し、環境調整や声かけなどの非拘束的ケアを優先する。
- 多職種で連携し、利用者の不安や危険行動の背景を把握して対応する。
8. 職員研修
- 年1回以上、全職員を対象に身体拘束廃止と適正化に関する研修を実施する。
- 研修では、禁止原則、3要件、事例検証、代替ケア方法等を取り扱う。
9. 指針の開示
本指針は事業所内に掲示し、利用者・家族・職員がいつでも閲覧できるようにする。
制定日:令和4年12月1日
改定日:令和4年12月1日
事業所名:訪問介護事業所ケアーズパートナー
管理者署名:岩田貴之
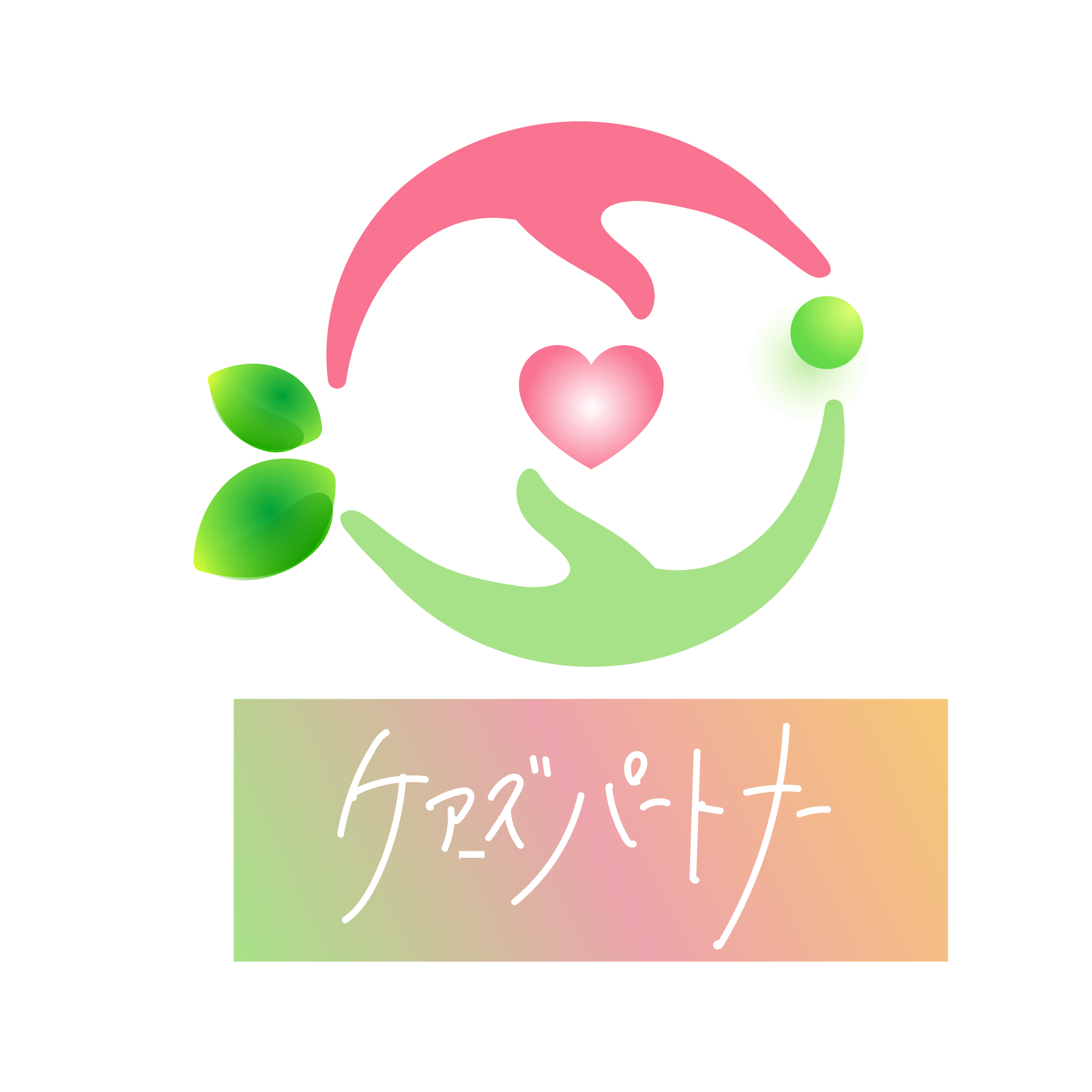
コメント